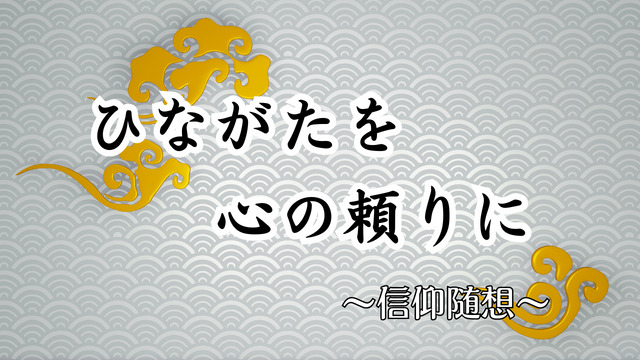コラム– category –
-

【信仰随想25】教祖百四十年祭に向けて 教区主事 駒谷欣一
本年は、教祖百四十年祭活動の仕上げの年、最後の一年であります。 私は教会長となって三度目の年祭を迎えますが、私の信仰の土台を築けたのは福岡での単独布教の頃だったと思います。 その八年間で一つだけ分かったことがあります。 それは、「棚からぼ... -

【陽気人の散歩道】おやさまの御前に
現在、私が主催している読書会がある。 読んでいる本は、稿本天理教教祖伝。 4人でスタートした読書会は、参加者の方がひとり誘ってこられて現在5人。 毎月2回、オンラインで開催している。 コロナ禍中に、SNSでつながった教友主催の教祖伝読書会に参加... -

【信仰随想24】おぢばへの日参 教区主事 横山常明
八木大教会初代会長、岸本又治郎先生は、瀕死のやけどをご守護頂かれてより、おぢばに近い大和八木の地に居を構え、仕事を終えては毎日おぢばにお礼に帰られました。 五代会長の祖父、六代会長の父もおぢばへの日参を続けていました。 私が会長になってか... -

【陽気人の散歩道】おぢばでのひのきしんのススメ
青年会員として最後の入隊 分会委員長を終えるにあたり、これまでお育て頂いた御礼の気持ちを込めて、おぢばでの伏せ込みに励もうと、12月12日に「おやさとふしん青年会ひのきしん隊」に入隊することになりました。 1日だけではありますが、隊員としての入... -

【信仰随想23】心定めてつとめきろう 教区主事 宇惠義司
今年は、年祭活動の三年目に当たり、ご本部より、心定めの完遂とおぢばがえりを特に意識してつとめてもらいたいとお示しいただきました。 私は、教祖が、心定めとぢばの理を改めてしっかり思案し、一手一つになってつとめるようにとお仕込みくださったもの... -

【陽気人の散歩道】地球の運動について
年が改まる。それは地球が太陽の周りを一周したということである。 これを地球の公転運動というが、恥ずかしながら私は、つい最近まで、教科書に書かれていた太陽系の図のように(図参照)、太陽の周りをぐるっと一周すると「元の位置に戻ってくる」ものと... -

【信仰随想22】フードバンクお礼 教区主事 岡本善弘
奈良教区の皆様、とりわけ婦人会の皆様には、フードバンク奈良への食品の提供誠にありがとうございます。 平成29年にフードバンク奈良が設立され、私は理事になって5年目になります。 上村善孝先生が教区長に就任されてから、奈良教区婦人会でフードバンク... -

【陽気人の散歩道】主人は御用、今日も留守。
結婚当初から、主人は御用で家にいないことが多々あり、泊まりで不在の時もあります。 結婚してからは、義両親と過ごす時間の方が長いのでは? とさえ感じています。(笑) 同じく教会のお嫁さんたちからも、度々そんな声を聞きます。 「いってらっし... -

【信仰随想21】日々実践 教区主事 山本道朗
私は若い頃、「自分は教祖のひながたのような通り方はできない」と思っていました。 そんな私の考えが大きく変わったのは、布教の家入寮中に前真柱様から聞かせていただいたお話でした。 前真柱様は私たち布教の家の寮生に「教祖が五十年のひながたの中で... -

【陽気人の散歩道】修養科の可能性
教祖140年祭に向かう年祭活動の2年目も終盤を迎えようとしているこの時期、一足早く旬を迎えたものがある。 第1000期を迎えた修養科である。 その歴史は、昭和16年4月に開設され、令和6年9月までの修養科修了者数の累計は、674,389人を数えるとの事。 去る... -

【信仰随想20】教祖なら 教区主事 山本忠治
私どもの教会では、「常に『教祖なら』、と行動しよう」と目標を掲げています。 ある教会長夫人がこんな話を聞かせてくれました。 教会の近所に八十代後半の他系統の信者Nさんが住んでおられ、毎月一日と月次祭には必ず教会に参拝されています。ある月... -

【陽気人の散歩道】信仰の醍醐味
親神様の十全の守護の中に「たいしょく天のみこと」があります。 その働きは「出産の時、親と子の胎縁を切り、出直しの時、息を引きとる世話、世界では切ること一切の守護の理」と教えられます。 このような教えを聞いていなければ、生活の中で「切ること...