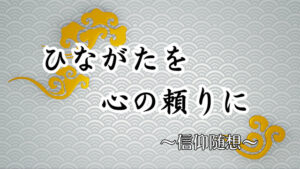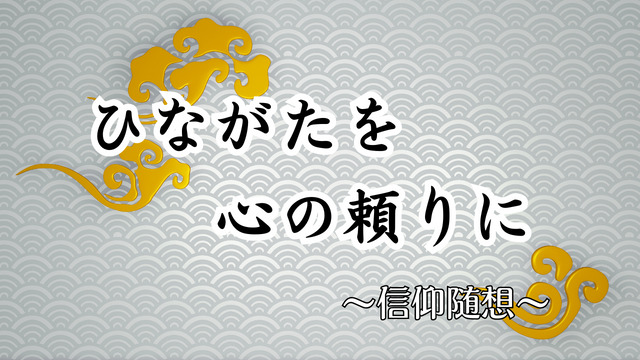
早いもので、教祖百四十年祭へ向かう年祭活動仕上げの年も折り返しを迎えた。
今年は年祭活動仕上げの年ということで、ご本部よりおぢばがえりが打ち出されている。
「斯道会」や「眞明組」といった集まりでの大型団参や、それぞれの教会でもおぢばがえりを計画し勇んでとりくんでいるかと思う。
自教会でも、5月25日に団参を実施し、大勢の方々とおぢばに帰らせていただいた。
当日は、みんなが懐かしい顔に逢うこともでき、たくさんの笑顔がおぢばに溢れ、大きな喜びを感じさせていただいた。
後に本席となられる飯降伊蔵先生が、妻おさとさんの産後の患いをおたすけいただくために初めておやしきへ帰ったときに教祖は、「さあゝ、待っていた、待っていた。」と仰せになっている。
教祖は、人々がたすけを願い教祖のもとへとやってきた時、度々「待っていた」と仰せになっている。
逸話篇10「えらい遠回りをして」では、夫・伊三郎さんの喘息をたすけていただくために教祖のもとへやってきた桝井キクさんに「待っていた、待っていた」とのお言葉をおかけになっている。
同じく、逸話篇33「国の架橋」では、息子・利三郎さんのたすかりを願う山本利八さんに、「おまえの来るのを、今日か明日かと待ってたのやで。」と仰せになっている。
私は、この教祖の「待っていた」というお言葉には、大きな、そして、温かな親心がこもっていると思う。
なんとかたすけてもらいたいとやってきた人を、まずは「待っていた」という言葉で労われる。
教祖にお会いした人がその言葉を聞くとどれだけ安心できたことだろう。
「よく来た」ではなく、「待っていた」というお言葉どおり、教祖はその人がたすかりに来るのを待っておられたということである。
教祖はその人がやってくる事を分かっておられたし、かわいい子どもをたすけてやりたいという親心でお待ちくだされていたのである。
もちろん、今もこれからもそのお心はけっして変わることはない。
おぢばで私たちの帰りを首を長くしてお待ちくだされているのが教祖である。
親は、離れて暮らす子供が帰ってきた時にとても嬉しいと思うものである。
かわいい子どもにあれもこれもしてやりたい、美味しいものをお腹いっぱい食べさせてやりたい、たくさんお土産を持たせてやりたい、このように考えるのが親である。
教祖は、年祭にひとりでも多くの子どもがおぢばに帰って来ることを楽しみにお待ちくだされている。
そして、私たちがおぢばに帰ったならば、必ず大きな御守護というお土産を準備してくだされている。
私は今、ブラジルへの巡教に向かう道中でこの原稿を書いている。
今回ブラジルまでの所要時間はフライトだけで約28時間、乗り継ぎ時間もあわせると40時間弱という長旅である。
そんなブラジルからも毎年大勢の人が教祖を慕いおぢばへお帰りになっている。
奈良教区では、11月30日に「奈良教区おぢばがえり団参」を実施する。
現在、各地で開催されている「ようぼく一斉活動日」の総仕上げとして、一人でも多くの方に教祖に逢いにおぢばへお帰りいただきたいと強く願う。