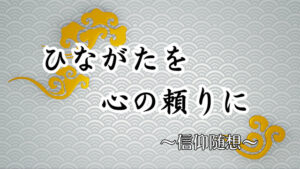「この教えを世界に広めていく」というとき、みなさんはどのようなイメージを持っておられますか?
たとえば、高野友治先生が収集した口伝になりますが、教祖はあるとき「神がはたらけば、世界一夜の間にもなむ天理王命にしてみせる」と仰ったそうです。
神様のお力で、一夜の間にも世界中の人が「なむ天理王命」と唱えてこの道を信仰するようになるということです。
その言葉を聞いた当時の信者さんたちは喜んで、そのようにしてくださいとお願いしました。
世界中の人が信仰するようになる姿は、まさに「陽気ぐらし」の完成に見えます。
私も喜んでお願いするでしょう。
すると、教祖は続けて「世界一夜の間になむ天理王命にしたところが、誰が修理肥に行ってくれますか」と尋ねられました。
修理とは農業用語で「田畑の手入れ」を意味します。
また、肥とは「肥料を施すこと」です。
つまり、教祖は農事に例えて「世界中の人がお道を信仰するようになったとき、その後は誰がその人たちの丹精に行ってくれますか?」と尋ねられたのです。
予想外の質問に戸惑ったのか、信者さんたちは答えられませんでした。
結果的に「親に代わって世界の人たちを育てさせてもらおう」という人は誰もいなかったのです。
そこで、教祖は「修理肥に行ってくれる人がなくてはどもならん、やめておこう」と仰ったとのことです(高野友治『教祖おおせには』2013年、26‐27頁)。
このお話からいろんなことが学べます。
(一)まず、このお話からすると、神様がその気になれば一夜の間に世界中の人が信仰する可能性があること。
そんなこと出来るのか、と思ってしまいますが、この世界を創造した神様なら当然といえば当然ともいえます。
(二)その上で、世界の人が信仰し始めるといっても、それはこの教えがただ情報として広まるのではないということ。
つまり、親が子を育てるように、この教えは人が人を育てることで伝わるのだと考えられます。
しかも、たとえ相手がこの道を信仰して「なむ天理王命」と唱えるようになったとしても、教祖はなおその人に対する「修理肥」すなわち丹精が必要だと仰せられています。
(三)そうだとすると「教えが広まる」ということは「育てる人」が増えることでもあるということ。
これがこのお話のポイントだと思います。
つまり、教祖はお一人で「育てる人」をお育てくださったのではないでしょうか。
この道は、歩み始めだけでなく、その後も共に歩むことが前提になっているのだと思います。
(四)そして育てることは、必要な時間をかけること。
つまり、世界は「一夜の間にも」変わる可能性がありつつも、同時に、時間をかけなければ育たないものがあるということ。
しかも、ただ時間をかければいいのではなく、育つために必要な時間のかけ方、順序があるのではないでしょうか。
だからこそ、教祖は「一夜の間にも」神様のお働きを見せることを控えられたのだと拝察します。
世界の人に教えを広めるために、いま私たちに何が必要なのでしょうか。
年祭まで残り一年。 (nibuno)