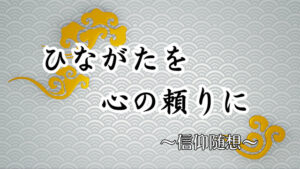現在、教祖百四十年祭へ向かう三年千日の年祭活動の一環として、5回の『ようぼく一斉活動日』の開催が打ち出され、すでに3回行われた。
各支部では、第4回目の5月31日(土)、6月1日(日)の開催に向けて準備が進んでいるところだと思います。
この度の『ようぼく一斉活動日』は、年祭活動期間中に複数回行うことや、活動内容等の中身は、各支部に委ねられている点がこれまで支部単位で行われてきた行事と大きく異なり、多くの支部で最初に開催の声が届いた時は、どうすればいいのか戸惑われたと推察します。
私の支部では、第1回の開催を前にどのような活動内容を計画すれば、支部内にお住まいのお道を信仰されている方達に多く参加してもらえ、また、参加者に年祭活動期間中であることを再認識してもらい、少しでも共々に年祭活動の歩みを進めてもらえるのかを支部長先生を中心に議論を重ねました。
そこで出た結論は、初めから5回行うことが決まっているのであれば、毎回変わる内容ではなく、
①最後まで一貫して行えること
②教祖の年祭活動期間中に相応しいこと
③参加される方達に少しでも何か持って帰ってもらえること
④お誘いの声かけをして下さる参加者の所属教会の方に喜んでもらえること
ザッとこのような理由で《おてふり練習》をプログラムに入れることに決まりました。
会場場所は、毎月の支部例会でも場所を提供して頂けている教会にご協力頂けることになり、行う内容と会場場所と順調に決まっていきました。
《おてふり練習》の進め方も開催当日の参加者数を150~200名と想定し、参加者本人におてふりの習得度で分けられた3つコースから選択してもらい、また、コース毎に決められた部屋へと移動してもらい、おてふり講師の指導の下、《おてふり練習》をしてもらうことになりました。
しかし、どのコースにどれくらいの参加者が分かれるのか、ある程度は予想し、その数に合わせて部屋を割り振ることはできましたが、予想が大きく外れた場合、1つにコースに参加者が集中し、部屋から参加者が溢れてしまい、収拾がつかない最悪のケースも考えられ、開催当日までどうなるのか不安を抱えたまま本番を迎えることになりました。
迎えた第1回目の当日、支部内の関係者が準備から本番まで協力し合い、誠真実を結集できたおかげか、心配されていた《おつとめ練習》も参加者が想定していた範囲内に収まるなど滞りなく終えることができました。
ところが、何事も問題ないかの様に進んでいた《おてふり練習》でしたが、参加者が一番多く選択したコースでは、部屋から人が溢れはしませんでしたが、うまく整列できずに重なりあってしまい、講師のおてふりがしっかりと見られない状況になっていました。
これでは大変申し訳ないと第1回目の反省を生かし、2回目以降は、2日間で一度だけだった開催を参加者の分散を図るため、一日に午前の部と午後の部と二度開催することとなりました。
各支部においても同様に回を重ねる度に工夫して行われている『ようぼく一斉活動日』ですが、この4月から教区では新しい教区長先生を迎え、新体制の下、第4回目の開催を迎えようとしています。
これまでの勢いのまま第5回までやり遂げ、教区の11月団参、そして、教祖百四十年祭の日を勇み心いっぱいで迎えられるように勤めたいと思います。(Pぇ~)