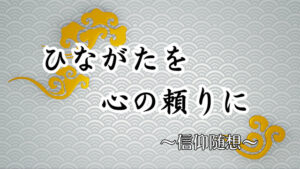長い歴史のある雅楽には、さまざまなエピソードが残されている。
人に関したもの、楽器に関したものなど。そうした中から少し取り上げて紹介したいと思う。
まず、最近、陰陽師(夢枕獏著)の小説で知っている方も多いと思うが、源博雅を取り上げてみたい。
陰陽師は安倍清明と源博雅の物語に仕上がっている。
清明と博雅は同時代の様だが、小説ほどの交流は無かったとのことのようである。
安倍清明は921~1005( 享年85)。
源博雅は918~980(享年63)となっている。
重なる年月は59年である。(幼少期を含む)
博雅の逸話は「今昔物語」に多く記されている。

まず、源博雅のプロフィールについて誌してみよう。
源博雅は、平安中期の公家であり雅楽家である。
西暦918年7月17日に克明親王(醍醐天皇の第一皇子、宇多天皇の孫)の長男として生まれる。
初め博雅王を名乗るが、のちに源朝臣姓を与えられて臣籍降下する。
臣籍降下したのは、母の身分が低かったとも言われている。
雅楽に優れ、筝を醍醐天皇に 琵琶を源脩に、笛は大石峯吉、篳篥は峯吉の子・富門、良峰行正に学んだ。
天延二年(974年)に従三位に叙せられる。
天元3年(980年)9月28日、薨去。享年63歳。
最終官位は従三位皇太后宮権大夫。ということである。
通称、博雅三位(はくがさんみ)、長秋卿。
管絃の名手といわれている。舞はしなかったようである。
また、村上天皇の勅で『新撰楽譜』(長秋卿笛譜・博雅笛譜)を著す。
現在よく退出音声として奏される「長慶子」は博雅の作曲である。
言い伝えによると酒に強く、酒豪であったようです。
また、朱雀門で鬼から名笛を得た話、琵琶の名器を羅生門から探し出した話、蝉丸のもとに通い琵琶の秘曲を伝授された話、など今昔物語に説話が残されています。