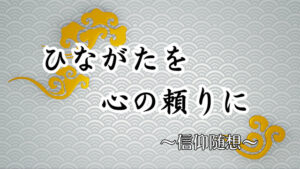年祭活動のこの旬に、存命の理がこもる赤衣について考えてみたい。
明治初期は、新政府によって天皇中心の国家神道が人々に強いられていた。
その中、明治7年10月のある日、教祖は、お屋敷に詰めていた二人の信者に「大和神社へ行き、どういう神で御座ると、尋ねておいで」と仰られた。
そして、そのことがきっかけで石上神宮の神職たちがお屋敷に来ることになり、教祖は「学問に無い、古い九億九万六千年間のこと、世界へ教えたい」と伝えられた。
その後、さらに奈良県庁の呼び出しを受けて、皇族ゆかりの円照寺に赴くことになったが、教祖はその場で「親神にとっては世界中は皆我が子、一列を一人も余さず救たすけたいのや」と仰せられた。
その2ヶ月後の12月26日、教祖は赤衣をお召しになった。
御年77歳で襦袢、腰巻、帯、足袋に至るまですべて赤いものを身につけられたのである。
そして、その日に4名の信者に身上たすけの「おさづけの理」を初めて渡された。
同年のおふでさき第6号では親神様の呼称が「神」から「月日」へと改められ、「十二月廿一日よりはなし」からおぢばの理と教祖の魂のいんねんについて説かれた上で、「このあかいきものなんとをもている なかに月日がこもりいるそや」(6‐63)と赤衣の意味合いについて記されている。
明治8年、こかん様の出直しをきっかけに天元講が結成されたが、そのとき教祖は「これを、信心のめどにして、お祀りしなされ」と仰せられて、お召しの赤衣の羽織を天元講の人々にお下げ下さった。
その後、個人や講社に対して度々赤衣をお下げ下さり、赤衣の一部は証拠守りとしてもお与え下さっている。
この年の6月には、ぢば定めが行われている。
明治7年入信の増井りん先生は、明治12年から教祖のお守役をすることになり、明治14年からは「針のしん」のお役を頂いている。
教祖の赤衣や証拠まもり、つとめ人衆の紋を縫うとき、増井先生が一針でも手にかけなければ理がないと伝えられている。
明治20年、教祖は現身を隠された。
3年経った頃には、お召し下ろしの赤衣はすべて渡してしまい、その後のことについて「おさしづ」を伺うと「赤き着物に仕立てゝ供え、これをお召し更え下されと願うて、それを以ていつく変わらん道という。(中略)姿は見えんだけやで、同んなし事やで、姿が無いばかりやで。(M23・3・17)」とのお言葉があった。
このように教祖は赤衣を通してさまざまなことを教えられておられる。
・世相に揺らぐことなく、親神様の元の思いを伝えること。
・ぢばの理、教祖の魂のいんねんを明らかにし、信仰の目標を明確にすること。
・その証拠に、赤衣やおさづけを通して具体的に人だすけの働きを現すこと。
・お屋敷では誠真実の心で、芯に合わせる態度で勤めること。
・さらに現身を隠されたのちまでも見据えて、これらのお働きがいつまでも変わらないことを赤衣を通して示されていること。
お召し物一つでこれだけのことを教えられているが、その理を受けるだけの成人がまだまだ足りないと感じられる。