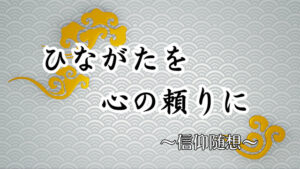楽器には、名器と呼ばれるものがあります。
雅楽における名器とはどのようなものでしょうか。
宮内庁元主席楽長・東儀俊美師が「名器への幻想」という文章を書かれていましたので紹介します。
(1)雅楽は五世紀の中頃、新羅の音楽が初めてその音を日本に響かせて以来、唐・百済 ・高句麗・林邑・天竺等様々な国から約三〇〇年以上の年月をかけて渡来し、幾多の変遷を経て「日本の雅楽」へと姿を変え、現在まで伝承されてきた。
渡来した当時は、勿論彼の国の人々が夫々の国から持ってきた楽器を用いて演奏したに違いない。
では、彼らはどんな楽器を使って演奏したのだろうか。
日本には当時の文献が無いので実際の処は解らないのだが、中国の唐時代の文献に残された楽器編成と、正倉院に残された楽器及びその破片から、ある程度のことは伺い知ることが出来る。
先ず唐時代の楽器編成を見ると、「天竺楽」には、楽用鞨鼓、篳篥、横笛、毛員鼓、都曇鼓、鳳首箜篌、琵琶、五絃琵琶、銅ばつ、その他。「高麗楽」には、楽用彈筝、しゅう箏、臥箜篌、堅箜篌、琵琶、五絃琵琶、笙、横笛、小篳篥、大篳篥、桃皮篳篥、簫、義嘴笛、腰鼓、斉鼓、担鼓、貝、その他。となっている。

演奏人数はほとんどの楽器が一人づつだが、天竺楽のなかで、篳篥、琵琶、五絃琵琶だけ二人になっている。
現在雅楽に使われている楽器より使われていない楽器の方が多いということは、現在演奏されている雅楽とは似ても似つかぬ音色と旋律だったと思われる。
また、唐時代の編成を見て気がつく不思議なことは、「天竺楽」には「笙」を使わず「高麗楽」では「笙」が使われていることである。
日本では全然反対に、「天竺楽」では「笙」を使い、「高麗楽」では使っていない。
では次に、正倉院に残されている楽器を見ると、琴、瑟、臥箜篌、五絃琵琶、阮咸、竿、方響、尺八、七絃楽器、二鼓、腰鼓。がある。
そして、日本の文献に名前だけ残る楽器名としては、堅笙筏、大角、小角、振鼓、四の鼓、拍盤、百子、銅鉢子等あるのだが、実物は存在しない(現在雅楽で使用されている楽器は除いた)。
唐楽、高麗楽、天竺楽、そして林邑楽も、最初は日本人が演奏したはずはない。
恐らくそれぞれの国の人達が、こうした様々な楽器を用いて賑やかに演奏したのだろう。