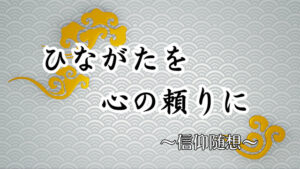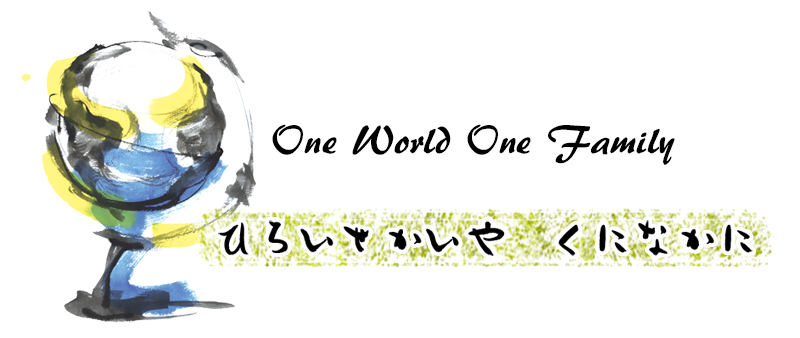
教祖130年祭の前日、21歳の私は関西国際空港に降り立った。
中国の蘇州という街での1年に渡る留学から帰国したのである。
留学生活での確かな成長、学び、達成感と寂しさで胸がいっぱいだったのを覚えている。
1年も生活をしていると衝撃的な経験もたくさんあった。
公道では車やバイクのクラクションが常に鳴り響いている。
行列に並んでいるのに平気で割り込みされる。
食事で出る骨や串は食卓や足元に投げ捨てる。
レストランのレジの前で集団が誰が奢るか掴み合いの喧嘩をしている。
どれも日本では考えられない、理解ができないことが日常茶飯事に起きた。
だが、私も生活をするなかで前述の行為は全て行った。
バイクに乗ればクラクションを積極的に鳴らしたし、行列への割り込みも時として行い、食事ででる骨や串も足元に投げ捨て、仲間と食事に行くと俺に支払わせろと喧嘩した。
なぜなら留学生の私が「郷に入っては郷に従う」ことは、異文化を理解する為の最も良い方法だからである。
日本ではどれも褒められることではない。
だが中国では褒められなければ怒られることでもない、日常茶飯事の文化なのである。

実践するなかで前述の行為には全て理由があることを私は知った。
皆日本人ほど交通ルールを守らないので、身を守るためにクラクションを鳴らす。
急いでいるなら行列に並ぶ時間がないので列に割り込む。
日本のように綺麗に食事する美徳はない。
日本人よりも遥かにメンツを重視しているため、仲間には奢りたいと思う。
実践してみると中国だと合理的に感じることも多く、その気づきが面白くもあった。
これを読んでいる方にもぜひ異文化を積極的に味わってもらいたい。
海外へ行く機会があれば進んで渡航し、肌で感じてもらいたい。
そんな機会がなければ、身近なところで異文化理解を生活に取り入れてみてほしい。
異文化理解をインターネットで調べると「文化の違いを認め、互いに尊重し、相互に理解しようとする態度のこと」と記載されている。
私は文化の違いというのは、何も国を超えずともご家庭や職場、町などの小さな単位で差異があるものだと思う。
ご近所さんや違う職業の方、歳の離れた方、立場の違う方と交流し、自身が持つ価値観に違いを見つけ、その違いを生活に取り入れていくことで得る気づきは、海外へ行くよりも小さい単位かもしれないが同様に面白いことだと思う。
身近な小さな単位で「郷に入り」、「郷に従う」ことで自身の持つ価値観に変化を与え、また他者を理解することで生活が豊かになると考える。(山本伸裕)